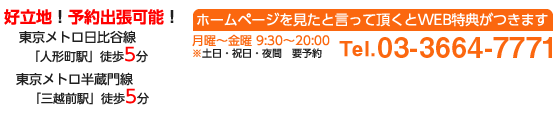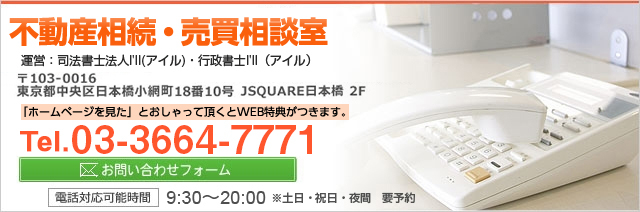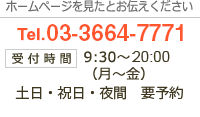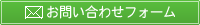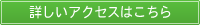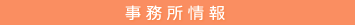所長ブログ
2013年9月10日 火曜日
遺留分
相続は亡くなられた方の意思を尊重して行われるものなので遺言があればそれに従がって行われますが、残された家族にも生活の保障を目的としてある限度で財産を受け取ることができる権利が認められており、それを遺留分と言います。
この遺留分は配偶者、子供、と直系尊属(父母や祖父母)に認められたものであり、兄弟には認められません。
遺留分は法定相続分と異なる割合で定められています。
場合分けを遺留分の割合を示すと以下のようになります。(すべて相続財産全体に対する割合です。)
○配偶者のみ 2分の1
○子供のみ 2分の1
○配偶者と子供 配偶者4分の1・子供8分の1
○配偶者と直系尊属 配偶者3分の1・直系尊属6分の1
○直系尊属のみ 3分の1
遺留分は放棄することも可能ですが、放棄しても他の相続人の割合が増えるということはありません。
遺留分が侵害されて相続が行われていた場合に、遺留分を受け取りたいと主張することを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます。
この請求は相続の開始及び減殺すべき遺贈や贈与があったことを知ったときから1年以内に行わなければなりません。また、それを知らなくても相続開始から10年が過ぎていると請求できなくなります。
最近、エンディングノートというものが流行っており、自分の死後どんなお葬式をしてほしいか、残った財産をどのように分けてほしいかなどを書き残すノートがあります。
亡くなられた方の意思が残された家族に伝わらなければ、争いのもとにもなりかねませんので、亡くなられる前に家族と話し合いをするということが大事だと思います。ちなみに遺留分の放棄は生前に行うことができますので、話し合いの結果、遺留分を侵害してしまうことになるならば、事前にそういった手続きを利用するのもトラブル回避の助けになると思います。
司法書士法人アイル事務員
utsuno
この遺留分は配偶者、子供、と直系尊属(父母や祖父母)に認められたものであり、兄弟には認められません。
遺留分は法定相続分と異なる割合で定められています。
場合分けを遺留分の割合を示すと以下のようになります。(すべて相続財産全体に対する割合です。)
○配偶者のみ 2分の1
○子供のみ 2分の1
○配偶者と子供 配偶者4分の1・子供8分の1
○配偶者と直系尊属 配偶者3分の1・直系尊属6分の1
○直系尊属のみ 3分の1
遺留分は放棄することも可能ですが、放棄しても他の相続人の割合が増えるということはありません。
遺留分が侵害されて相続が行われていた場合に、遺留分を受け取りたいと主張することを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます。
この請求は相続の開始及び減殺すべき遺贈や贈与があったことを知ったときから1年以内に行わなければなりません。また、それを知らなくても相続開始から10年が過ぎていると請求できなくなります。
最近、エンディングノートというものが流行っており、自分の死後どんなお葬式をしてほしいか、残った財産をどのように分けてほしいかなどを書き残すノートがあります。
亡くなられた方の意思が残された家族に伝わらなければ、争いのもとにもなりかねませんので、亡くなられる前に家族と話し合いをするということが大事だと思います。ちなみに遺留分の放棄は生前に行うことができますので、話し合いの結果、遺留分を侵害してしまうことになるならば、事前にそういった手続きを利用するのもトラブル回避の助けになると思います。
司法書士法人アイル事務員
utsuno
投稿者 司法書士法人I'll