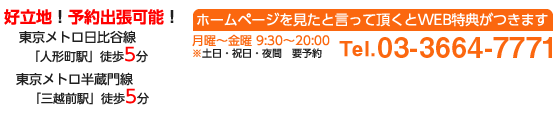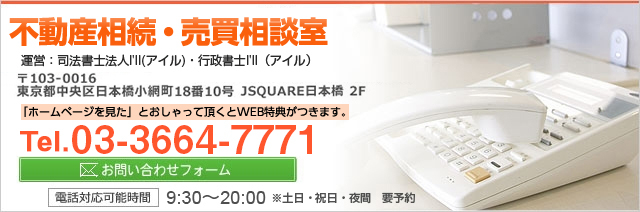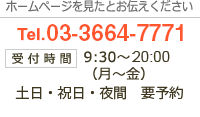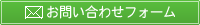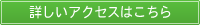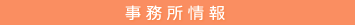所長ブログ
2013年9月27日 金曜日
婚外子の記載
先日、非嫡出子の法定相続分が嫡出子の2分の1であるというのは違憲であると判断されましたが、昨日別の裁判において、出生届の記載に婚外子かどうかを記載するのは違憲とはいえないという判断がされました。
婚姻数が減り、嫡出子でない子が増えている中で、家族の形態が変化したとしても、子どもの権利は守られるべきであると思いますし、子どもは平等に扱われるべきであると思います。
事実上夫婦関係を築き、同じ家で生活し、子どもをもうけるならば、婚姻届の1枚くらい提出してしまえばいいのにと私は思ってしまうのですが、それはそのカップルによってそれぞれの事情や考え方があるのでしょう。
婚姻届、紙切れ1枚で何も変わらないような気もしますが、その1枚で夫婦であるということが公に証明がされて、税金や社会保険、相続などの手続きはおおいに楽になると思うのですが・・・それをも考慮して紙切れ1枚を提出しないのは、やはりそれ自体がこれまでの夫婦関係とは異なる、新しい家族の形が出来上がっているのではないかと思います。
公的な手続きというものは全般的にめんどくさいものが多いですが、それをいちからきちんと行うことに意義があると私は考えます。誰か1人だけ手続きを省いてしまってもあまり問題はないと思います。しかし、それが大多数となれば、社会システムは混乱すると思います。「誰か1人」を特定の人に決めることはできないから、全員が平等に、たとえ形式的なことであっても、めんどくさい手続きを行うべきなのだと考えます。
法律をはじめとする規則に従うということは、社会の秩序を保つために必要なことなのではないかと思います。
司法書士法人アイル 事務員
utsuno
婚姻数が減り、嫡出子でない子が増えている中で、家族の形態が変化したとしても、子どもの権利は守られるべきであると思いますし、子どもは平等に扱われるべきであると思います。
事実上夫婦関係を築き、同じ家で生活し、子どもをもうけるならば、婚姻届の1枚くらい提出してしまえばいいのにと私は思ってしまうのですが、それはそのカップルによってそれぞれの事情や考え方があるのでしょう。
婚姻届、紙切れ1枚で何も変わらないような気もしますが、その1枚で夫婦であるということが公に証明がされて、税金や社会保険、相続などの手続きはおおいに楽になると思うのですが・・・それをも考慮して紙切れ1枚を提出しないのは、やはりそれ自体がこれまでの夫婦関係とは異なる、新しい家族の形が出来上がっているのではないかと思います。
公的な手続きというものは全般的にめんどくさいものが多いですが、それをいちからきちんと行うことに意義があると私は考えます。誰か1人だけ手続きを省いてしまってもあまり問題はないと思います。しかし、それが大多数となれば、社会システムは混乱すると思います。「誰か1人」を特定の人に決めることはできないから、全員が平等に、たとえ形式的なことであっても、めんどくさい手続きを行うべきなのだと考えます。
法律をはじめとする規則に従うということは、社会の秩序を保つために必要なことなのではないかと思います。
司法書士法人アイル 事務員
utsuno
投稿者 司法書士法人I'll | 記事URL
2013年9月20日 金曜日
債務整理について
債務整理の方法は大きく分けて4つあります。
・任意整理
弁護士や司法書士が代理人となって、金融機関などの債権者と話し合いにより、借金を減額したり、分割払いにしてもったりする方法です。裁判所を利用しない方法です。
・特定調停
簡易裁判所に申し立てることで、裁判所が調停員を立て、債権者と債務者の話し合いを仲裁し、返済条件の緩和等の合意が成立するようにしてくれます。
・自己破産
借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、借金の返済を免責してもらうことができます。現在ある財産は没収されてしまうといったデメリットはありますが、借金の支払いから解放されます。
・民事再生
住宅を手放さずに、住宅ローン以外の借金を減額し、原則3年間で分割して返済していく方法です。3年間で返済しなくてはならないので、継続的な収入の見込みがなければなりません。
それぞれの方法にメリットとデメリットがありますので、自己の状況に応じてどの手続きを利用するかを決めていく必要があります。
司法書士法人アイル事務員
utsuno
・任意整理
弁護士や司法書士が代理人となって、金融機関などの債権者と話し合いにより、借金を減額したり、分割払いにしてもったりする方法です。裁判所を利用しない方法です。
・特定調停
簡易裁判所に申し立てることで、裁判所が調停員を立て、債権者と債務者の話し合いを仲裁し、返済条件の緩和等の合意が成立するようにしてくれます。
・自己破産
借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、借金の返済を免責してもらうことができます。現在ある財産は没収されてしまうといったデメリットはありますが、借金の支払いから解放されます。
・民事再生
住宅を手放さずに、住宅ローン以外の借金を減額し、原則3年間で分割して返済していく方法です。3年間で返済しなくてはならないので、継続的な収入の見込みがなければなりません。
それぞれの方法にメリットとデメリットがありますので、自己の状況に応じてどの手続きを利用するかを決めていく必要があります。
司法書士法人アイル事務員
utsuno
投稿者 司法書士法人I'll | 記事URL
2013年9月17日 火曜日
代襲相続
代襲相続という言葉は相続の機会がなければ耳にしない言葉だと思いますが、相続では基本的な知識かと思います。
言葉だけを見ると画数も多くて難しそうに感じますが、内容は難しくありません。
例えば、不幸にも親よりも先に子供が亡くなり、その後、親が亡くなった際に、孫が代わりに財産を相続できます。
まず、代襲相続ができる人は、
・相続人の子ども(被相続人にとっての孫)、その次は孫、曾孫、玄孫・・・
もしくは
・被相続人の兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥や姪)
となります。(直系尊属は代襲相続はできません。)
代襲相続ができる場合は以下のような条件になります。
・被相続人の子どもが相続時に亡くなっていた場合
・相続人が欠格事由(民法891条)に該当していた場合
・相続人が廃除(民法892条・893条)に該当していた場合
以上の3つのうちどれかが当てはまると代襲相続ができます。ただし、相続人が相続放棄をした場合は代襲相続できません。
相続人の代わりに相続するという意味ですので、相続分は相続人の法定相続分と同じになります。
司法書士法人アイル事務員
utsuno
言葉だけを見ると画数も多くて難しそうに感じますが、内容は難しくありません。
例えば、不幸にも親よりも先に子供が亡くなり、その後、親が亡くなった際に、孫が代わりに財産を相続できます。
まず、代襲相続ができる人は、
・相続人の子ども(被相続人にとっての孫)、その次は孫、曾孫、玄孫・・・
もしくは
・被相続人の兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥や姪)
となります。(直系尊属は代襲相続はできません。)
代襲相続ができる場合は以下のような条件になります。
・被相続人の子どもが相続時に亡くなっていた場合
・相続人が欠格事由(民法891条)に該当していた場合
・相続人が廃除(民法892条・893条)に該当していた場合
以上の3つのうちどれかが当てはまると代襲相続ができます。ただし、相続人が相続放棄をした場合は代襲相続できません。
相続人の代わりに相続するという意味ですので、相続分は相続人の法定相続分と同じになります。
司法書士法人アイル事務員
utsuno
投稿者 司法書士法人I'll | 記事URL
2013年9月12日 木曜日
資源ごみの違法回収
今朝のテレビで、資源ごみを自治体以外の団体が持ち去る事例が増えており、そのような行為は違法であるということを知りました。
たしかに私の住んでいる地域でも、資源ごみの回収の日の前夜と早朝に車で資源ごみを回収していく人がいます。
ごみを出す方としては、ごみを持っていってくれていることに変わりはないので、誰が回収しようが問題ないと思っていましたが、このような行為は違法だそうです。
各自治体のほとんどで条例が定められており、所定の場所に出されたごみは自治体の所有物となり、回収してはいけないそうです。
そして、このような資源ごみは自治体によって回収されると、その後リサイクルセンターなどで換金され、自治体の大事な収入源のひとつとなるそうです。
しかし、違法なごみの持ち去りをしている人たちは、海外のリサイクル業者に売り渡すことで私腹を肥やし、また資源ごみは海外に渡ってしまうので、日本で資源としてリサイクルされなくなります。
こういったことを聞くと、自分に関係のない話ではないなと思いませんか?
ちなみに、新聞などの紙の資源ごみは1キロで7~8円程度で、一家庭の1か月の新聞は10キロほどなので70~80円に換金できるそうです。
どれが自治体の正規の回収車なのか、何時ごろに回収に来るのかわかりづらい地域も多いと思いますが、資源ごみ回収日の当日の朝に出すことを心がければある程度の対策にはなると思います。
司法書士法人アイル事務員
utsuno
たしかに私の住んでいる地域でも、資源ごみの回収の日の前夜と早朝に車で資源ごみを回収していく人がいます。
ごみを出す方としては、ごみを持っていってくれていることに変わりはないので、誰が回収しようが問題ないと思っていましたが、このような行為は違法だそうです。
各自治体のほとんどで条例が定められており、所定の場所に出されたごみは自治体の所有物となり、回収してはいけないそうです。
そして、このような資源ごみは自治体によって回収されると、その後リサイクルセンターなどで換金され、自治体の大事な収入源のひとつとなるそうです。
しかし、違法なごみの持ち去りをしている人たちは、海外のリサイクル業者に売り渡すことで私腹を肥やし、また資源ごみは海外に渡ってしまうので、日本で資源としてリサイクルされなくなります。
こういったことを聞くと、自分に関係のない話ではないなと思いませんか?
ちなみに、新聞などの紙の資源ごみは1キロで7~8円程度で、一家庭の1か月の新聞は10キロほどなので70~80円に換金できるそうです。
どれが自治体の正規の回収車なのか、何時ごろに回収に来るのかわかりづらい地域も多いと思いますが、資源ごみ回収日の当日の朝に出すことを心がければある程度の対策にはなると思います。
司法書士法人アイル事務員
utsuno
投稿者 司法書士法人I'll | 記事URL
2013年9月10日 火曜日
遺留分
相続は亡くなられた方の意思を尊重して行われるものなので遺言があればそれに従がって行われますが、残された家族にも生活の保障を目的としてある限度で財産を受け取ることができる権利が認められており、それを遺留分と言います。
この遺留分は配偶者、子供、と直系尊属(父母や祖父母)に認められたものであり、兄弟には認められません。
遺留分は法定相続分と異なる割合で定められています。
場合分けを遺留分の割合を示すと以下のようになります。(すべて相続財産全体に対する割合です。)
○配偶者のみ 2分の1
○子供のみ 2分の1
○配偶者と子供 配偶者4分の1・子供8分の1
○配偶者と直系尊属 配偶者3分の1・直系尊属6分の1
○直系尊属のみ 3分の1
遺留分は放棄することも可能ですが、放棄しても他の相続人の割合が増えるということはありません。
遺留分が侵害されて相続が行われていた場合に、遺留分を受け取りたいと主張することを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます。
この請求は相続の開始及び減殺すべき遺贈や贈与があったことを知ったときから1年以内に行わなければなりません。また、それを知らなくても相続開始から10年が過ぎていると請求できなくなります。
最近、エンディングノートというものが流行っており、自分の死後どんなお葬式をしてほしいか、残った財産をどのように分けてほしいかなどを書き残すノートがあります。
亡くなられた方の意思が残された家族に伝わらなければ、争いのもとにもなりかねませんので、亡くなられる前に家族と話し合いをするということが大事だと思います。ちなみに遺留分の放棄は生前に行うことができますので、話し合いの結果、遺留分を侵害してしまうことになるならば、事前にそういった手続きを利用するのもトラブル回避の助けになると思います。
司法書士法人アイル事務員
utsuno
この遺留分は配偶者、子供、と直系尊属(父母や祖父母)に認められたものであり、兄弟には認められません。
遺留分は法定相続分と異なる割合で定められています。
場合分けを遺留分の割合を示すと以下のようになります。(すべて相続財産全体に対する割合です。)
○配偶者のみ 2分の1
○子供のみ 2分の1
○配偶者と子供 配偶者4分の1・子供8分の1
○配偶者と直系尊属 配偶者3分の1・直系尊属6分の1
○直系尊属のみ 3分の1
遺留分は放棄することも可能ですが、放棄しても他の相続人の割合が増えるということはありません。
遺留分が侵害されて相続が行われていた場合に、遺留分を受け取りたいと主張することを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます。
この請求は相続の開始及び減殺すべき遺贈や贈与があったことを知ったときから1年以内に行わなければなりません。また、それを知らなくても相続開始から10年が過ぎていると請求できなくなります。
最近、エンディングノートというものが流行っており、自分の死後どんなお葬式をしてほしいか、残った財産をどのように分けてほしいかなどを書き残すノートがあります。
亡くなられた方の意思が残された家族に伝わらなければ、争いのもとにもなりかねませんので、亡くなられる前に家族と話し合いをするということが大事だと思います。ちなみに遺留分の放棄は生前に行うことができますので、話し合いの結果、遺留分を侵害してしまうことになるならば、事前にそういった手続きを利用するのもトラブル回避の助けになると思います。
司法書士法人アイル事務員
utsuno
投稿者 司法書士法人I'll | 記事URL
2013年9月 9日 月曜日
相続分
先日、最高裁判所において、非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1は違憲であるという判決が下されました。現代の家族の形の多様化に即した判断だと思います。
さて、非嫡出子は嫡出子と同じ割合で相続が認められましたが、身内の方が亡くなられて自分の相続分はいくらになるかということを考えたときに正しく求められるでしょうか。
法律によって定められる相続分つまり法定相続分は以下のように場合にわけて考えられます。まずは亡くなられた方に配偶者がいるかどうかで2つに分けて考えるとわかりやすいと思います。
○亡くなられた方に配偶者がいる場合
1) 亡くなられた方に子供や父母、兄弟が全くいない場合
配偶者1
2) 子供がいる場合
配偶者2分の1 子供2分の1
3) 子供がおらず、父母がいる場合
配偶者3分の2 父母3分の1
4) 子供と父母がおらず、兄弟がいる場合
配偶者4分の3 兄弟4分の1
○亡くなられた方に配偶者がいない場合
1)子供がいる場合
子供1
2)子供がおらず父母がいる
父母1
3)子供、父母がおらず、兄弟がいる
兄弟1
今回の最高裁の判決で非嫡出子は嫡出子と区別せずに考えられることになりましたので、上記で言うと「子供」として分類されます。
ちなみに義理の子供(つまりお嫁さんやお婿さん)は法定相続人ではありません。
また、法定相続はあくまで法律が定めたものであり、実際には被相続人の意思が尊重されるので必ずもらえるものではありません。また、相続人間での話し合いで相続分が変わる可能性もあります。
司法書士法人アイル 事務員
utsuno
さて、非嫡出子は嫡出子と同じ割合で相続が認められましたが、身内の方が亡くなられて自分の相続分はいくらになるかということを考えたときに正しく求められるでしょうか。
法律によって定められる相続分つまり法定相続分は以下のように場合にわけて考えられます。まずは亡くなられた方に配偶者がいるかどうかで2つに分けて考えるとわかりやすいと思います。
○亡くなられた方に配偶者がいる場合
1) 亡くなられた方に子供や父母、兄弟が全くいない場合
配偶者1
2) 子供がいる場合
配偶者2分の1 子供2分の1
3) 子供がおらず、父母がいる場合
配偶者3分の2 父母3分の1
4) 子供と父母がおらず、兄弟がいる場合
配偶者4分の3 兄弟4分の1
○亡くなられた方に配偶者がいない場合
1)子供がいる場合
子供1
2)子供がおらず父母がいる
父母1
3)子供、父母がおらず、兄弟がいる
兄弟1
今回の最高裁の判決で非嫡出子は嫡出子と区別せずに考えられることになりましたので、上記で言うと「子供」として分類されます。
ちなみに義理の子供(つまりお嫁さんやお婿さん)は法定相続人ではありません。
また、法定相続はあくまで法律が定めたものであり、実際には被相続人の意思が尊重されるので必ずもらえるものではありません。また、相続人間での話し合いで相続分が変わる可能性もあります。
司法書士法人アイル 事務員
utsuno
投稿者 司法書士法人I'll | 記事URL