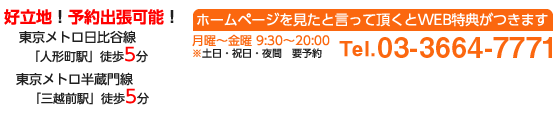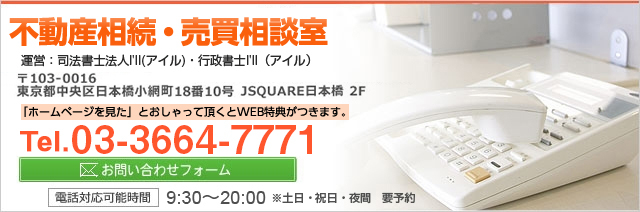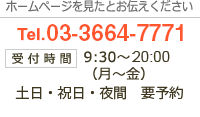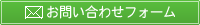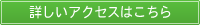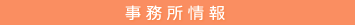所長ブログ
2013年10月24日 木曜日
クレームと謝罪
仕事上においてミスをして、お客様に謝罪することはどんな仕事でもありますし、失敗は誰にでもあるので、避けられないと思います。
失敗に対して、次はこのようなことがないように気を付けようと反省し、自分を戒めることはできますが、そういった気持ちがあったとしても迷惑をかけてしまったお客様へどのように謝罪すれば誠意が伝わるのかというのは難しく感じます。
ここ最近のニュースで、お客さんが店員に土下座をさせて逮捕されたというものや、生徒の親が教師に土下座をさせて逮捕されたという報道を目にしました。
土下座をさせる行為は刑法223条1項の強要罪に該当するようです。強要罪の条文を見ると、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と規定されています。
この条文によれば、脅迫をして、人に義務のないことを行わせることが強要罪に該当するので、土下座は店員さんにとってお客さんにしなければならない謝罪方法ではないということだとわかります。
私は実際に土下座をする人はフィクションやテレビのバラエティ番組でしか存在しないものだと考えていましたが、実際に土下座をしたり、させたりすることがあり、それが謝罪の形として納得できるものだと感じている人がいることに驚きを感じました。
私は土下座をするよりももっと現実的で効果的な謝罪方法があるような気がします。ひざまずかれて謝られてもうれしい気持ちはしません。
土下座をさせる場面でもそうですが、損害賠償を求める裁判においても、賠償金と謝罪を求める人がいますが、謝罪を相手にさせること事態なんだか本末転倒な気がします。相手に謝罪の言葉を言わせればすっきりするものなのでしょうか・・・。
司法書士法人I'll 事務員
失敗に対して、次はこのようなことがないように気を付けようと反省し、自分を戒めることはできますが、そういった気持ちがあったとしても迷惑をかけてしまったお客様へどのように謝罪すれば誠意が伝わるのかというのは難しく感じます。
ここ最近のニュースで、お客さんが店員に土下座をさせて逮捕されたというものや、生徒の親が教師に土下座をさせて逮捕されたという報道を目にしました。
土下座をさせる行為は刑法223条1項の強要罪に該当するようです。強要罪の条文を見ると、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と規定されています。
この条文によれば、脅迫をして、人に義務のないことを行わせることが強要罪に該当するので、土下座は店員さんにとってお客さんにしなければならない謝罪方法ではないということだとわかります。
私は実際に土下座をする人はフィクションやテレビのバラエティ番組でしか存在しないものだと考えていましたが、実際に土下座をしたり、させたりすることがあり、それが謝罪の形として納得できるものだと感じている人がいることに驚きを感じました。
私は土下座をするよりももっと現実的で効果的な謝罪方法があるような気がします。ひざまずかれて謝られてもうれしい気持ちはしません。
土下座をさせる場面でもそうですが、損害賠償を求める裁判においても、賠償金と謝罪を求める人がいますが、謝罪を相手にさせること事態なんだか本末転倒な気がします。相手に謝罪の言葉を言わせればすっきりするものなのでしょうか・・・。
司法書士法人I'll 事務員
投稿者 司法書士法人I'll | 記事URL
2013年10月21日 月曜日
不動産登記
不動産の登記簿謄本は不動産に係る仕事をしていないとなかなか目にしないものだと思います。マイホームを建てたり、購入したり、親族の不動産を相続したりといった状況にならなければどういうものなのかわからない方も多いと思います。私も不動産登記法の勉強をするまで見たことがなかったため、不動産登記を言うものをイメージしづらかったです。
最初に登記簿謄本と書きましたが、現在は登記がすべてデジタルデータとして扱われているため、これまでのような紙の束である登記簿謄本はなくなり、登記事項証明書というものが発行されるようになりました。これを法務局で取得すると、不動産の権利関係を確認することができます。
不動産登記は主に、土地と建物の権利関係を表示するものです。登記しなければ権利が発生しないというわけではありませんが、登記をすることによって第三者にこれは自分の所有物であるなどと権利を主張できます。また、抵当権等がついている場合、この不動産には担保権が付属しているということを警告する機能もあります。
登記事項証明書には大きく分けて3つの項目があります。すなわち、表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)の3つです。
表題部とは土地や建物がどこに存在しているものか、どのような不動産なのかを表示する項目です。
甲区は所有権を表示する部分です。ここを見ると、いつ誰がどのような原因でこの不動産を取得したのかを確認できます。
乙区は抵当権などの所有権以外の権利が表示されています。ここをみると、所有権以外にどんな権利が付着しているのかを確認することができます。
ちなにみに、記載されている事項に下線が引かれていた場合、その内容が削除されたり、変更されたことを意味しています。
司法書士法人I'll 事務員
utsuno
最初に登記簿謄本と書きましたが、現在は登記がすべてデジタルデータとして扱われているため、これまでのような紙の束である登記簿謄本はなくなり、登記事項証明書というものが発行されるようになりました。これを法務局で取得すると、不動産の権利関係を確認することができます。
不動産登記は主に、土地と建物の権利関係を表示するものです。登記しなければ権利が発生しないというわけではありませんが、登記をすることによって第三者にこれは自分の所有物であるなどと権利を主張できます。また、抵当権等がついている場合、この不動産には担保権が付属しているということを警告する機能もあります。
登記事項証明書には大きく分けて3つの項目があります。すなわち、表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)の3つです。
表題部とは土地や建物がどこに存在しているものか、どのような不動産なのかを表示する項目です。
甲区は所有権を表示する部分です。ここを見ると、いつ誰がどのような原因でこの不動産を取得したのかを確認できます。
乙区は抵当権などの所有権以外の権利が表示されています。ここをみると、所有権以外にどんな権利が付着しているのかを確認することができます。
ちなにみに、記載されている事項に下線が引かれていた場合、その内容が削除されたり、変更されたことを意味しています。
司法書士法人I'll 事務員
utsuno
投稿者 司法書士法人I'll | 記事URL
2013年10月18日 金曜日
日本酒乾杯条例
最近様々な地域で日本酒乾杯条例というものが制定されているというの聞きました。これは乾杯の際に日本酒を飲むように勧めることで、日本酒を多くの人に飲んでもらい、日本独自のお酒である日本酒の普及を促進させようという意図から制定されています。
条例と言っても乾杯の際のお酒を日本酒に強制するわけでも、罰則があるわけでもないそうです。
私もお酒が好きで、日本酒も飲みますが、条例があったとしても最初の一杯で日本酒を飲もうと思いません。個人的な意見ですが、最初の乾杯はアルコール度数が低めで、あっさりとしたものの方が良い気がします。日本酒は中盤に飲みたいお酒です。
日本酒をもっと多くの人に飲んでもらいたいという気持ちもわかりますし、日本酒が広まれば地域の活性化にもつながっていくとは思いますが、この条例によってこれまで乾杯をビールでしていた人々が日本酒でという気になるか疑問があります。
日本酒の普及を目的とするならばもっと効果的な手段があるように思いますが、少なくともこのような条例が各地で制定されているという事実が広まることで、日本酒の消費量が減っていることを知り、日本酒をもっと飲もうという気持ちになる人も少なくないのではと期待します。
司法書士法人I'll 事務員
utsuno
条例と言っても乾杯の際のお酒を日本酒に強制するわけでも、罰則があるわけでもないそうです。
私もお酒が好きで、日本酒も飲みますが、条例があったとしても最初の一杯で日本酒を飲もうと思いません。個人的な意見ですが、最初の乾杯はアルコール度数が低めで、あっさりとしたものの方が良い気がします。日本酒は中盤に飲みたいお酒です。
日本酒をもっと多くの人に飲んでもらいたいという気持ちもわかりますし、日本酒が広まれば地域の活性化にもつながっていくとは思いますが、この条例によってこれまで乾杯をビールでしていた人々が日本酒でという気になるか疑問があります。
日本酒の普及を目的とするならばもっと効果的な手段があるように思いますが、少なくともこのような条例が各地で制定されているという事実が広まることで、日本酒の消費量が減っていることを知り、日本酒をもっと飲もうという気持ちになる人も少なくないのではと期待します。
司法書士法人I'll 事務員
utsuno
投稿者 司法書士法人I'll | 記事URL
2013年10月 8日 火曜日
地域ブランド
今年、三重県の伊勢神宮が式年遷宮の年だということで、テレビでよく取り上げられていました。
三重県で有名なもののひとつに「松坂牛」がありますが、最近テレビを見ているとこれを「まつさかうし」と読んでいることに少し疑問を持ちました。私の記憶に間違えがなければ、以前は「まつざかぎゅう」と読んでいた気がします。
気になって調べてみたのですが、この松坂牛は2007年に地域団体商標というものに登録され、その際「まつさかうし」として登録されたようです。
もともと地元の人には「まつさかうし」と呼ばれており、その読み方で登録されたようです。
これに合わせ、メディアでは「まつさかうし」と統一して呼ぶようになったのだと思います。
いつの間にか示し合わせたようにこぞってこれまでの読み方を変えられると違和感を抱くものです。
この地域団体商標というのは、いわゆる地域ブランドと言って、地域の特産品を他の地域と差別化することでブランド化し、地域の活性化に役立っているものです。
もともと、商標は地域の名前や単なる物の名称では登録できないことになっていますが、地域団体商標は特別に設けられた制度です。
司法書士法人I'll事務員
utsuno
三重県で有名なもののひとつに「松坂牛」がありますが、最近テレビを見ているとこれを「まつさかうし」と読んでいることに少し疑問を持ちました。私の記憶に間違えがなければ、以前は「まつざかぎゅう」と読んでいた気がします。
気になって調べてみたのですが、この松坂牛は2007年に地域団体商標というものに登録され、その際「まつさかうし」として登録されたようです。
もともと地元の人には「まつさかうし」と呼ばれており、その読み方で登録されたようです。
これに合わせ、メディアでは「まつさかうし」と統一して呼ぶようになったのだと思います。
いつの間にか示し合わせたようにこぞってこれまでの読み方を変えられると違和感を抱くものです。
この地域団体商標というのは、いわゆる地域ブランドと言って、地域の特産品を他の地域と差別化することでブランド化し、地域の活性化に役立っているものです。
もともと、商標は地域の名前や単なる物の名称では登録できないことになっていますが、地域団体商標は特別に設けられた制度です。
司法書士法人I'll事務員
utsuno
投稿者 司法書士法人I'll | 記事URL
2013年10月 1日 火曜日
成年後見人制度
成年後見とは認知症や知的障害等により判断能力が不十分な方に代わって、後見人が財産の管理や遺産分割協議の参加、様々な契約の締結などを行い、判断能力が低下した方々を保護する制度です。
成年後見人制度には法定後見人制度と任意後見人制度の2種類あります。
法定後見人制度は、本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助と3つに分けられ、家庭裁判所が選任した後見人が本人をサポートします。
一方、任意後見人制度は、判断能力が低下する前に、予め自分の選んだ後見人に万が一の場合は代理権を付与するという契約を結んでおくものです。
司法書士法人I'll事務員
utsuno
成年後見人制度には法定後見人制度と任意後見人制度の2種類あります。
法定後見人制度は、本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助と3つに分けられ、家庭裁判所が選任した後見人が本人をサポートします。
一方、任意後見人制度は、判断能力が低下する前に、予め自分の選んだ後見人に万が一の場合は代理権を付与するという契約を結んでおくものです。
司法書士法人I'll事務員
utsuno
投稿者 司法書士法人I'll | 記事URL